「ブラック企業で右往左往です」
北海道知床沖で26人の乗員乗客とともに行方不明になっていた観光船「KAZU I(カズワン)」の豊田徳幸船長は今年3月、Facebookにこんな愚痴を投稿した。
この言葉を裏付けるように、運営会社「知床遊覧船」のブラックぶりが次々と明らかになっている。まず、日本中が衝撃を受けたのが、荒天の予報が出て、同業者がみな船を出すことをあきらめていた中で、カズワンだけが“強行運航”したことである。
なぜこんなことをしたのか真相はまだ明らかになっていないが、同業者からは「運航できる」と判断をした桂田社長に対して、弱い立場の豊田船長が断れなかったのではないかと指摘する声が多い。社長から厳しいノルマを押し付けられて、安全性をないがしろにするのも、ブラック企業の定番だ。
世間が驚いた同社のブラックぶりは、これだけではない。21年だけでも2度も座礁事故などを繰り返していたにもかかわらず、GPS装置も衛星電話も積んでいなかった。事務所に設置されていた無線のアンテナも折れたままで、カズワンが海上保安庁に救助要請した際も、乗客の携帯電話が使われた。「安全」を担保するためのコストをとことんケチるのも、ブラック企業でよく見られる現象だ。
ただ、安全を軽視しているのはこの会社だけではない。埼玉県のあるバス会社に勤務する高速バス運転手が走行中に「ながらスマホ」をしていることが分かった。路肩にはみ出るような危険運転を乗客が注意すると、「いじってねえよ」「マナーの悪い客だな」などと逆ギレされたという。
そんな観光業者のずさんな実態が次々と明らかになると、GWや夏休みで観光を楽しもうという人たちはこんな風に思うのではないだろうか。家族や大切な人と安全に旅をするために、知床遊覧船のような「観光ブラック企業」を見抜くいい方法はないだろか――。
関連記事
公式WebサイトやSNSの更新
今回、悲劇に襲われた人たちはみな、知床遊覧船がここまでひどい会社だと知ることもなく、カズワンに乗り込んでしまった。公式Webサイトをチェックしても、同業者と同じように、美しい知床の写真が多く使われていて、同じような情報しか掲載されていない。また、「安全への取り組み」として「知床小型船協議会加入」「船客障害賠償責任保険加入」「知床小型船協議会合同安全訓練毎年実施」などという文字も並んでいるので、なんとなくちゃんとした会社だという印象を受けてしまう。
また、荒天の予報に関しても、知床に初めて訪れる観光客からすれば、地元の観光船が運航しているというだけで、「きっと安全なのだろう」と信頼してしまう。
つまり、われわれ一般の観光客が入手できるような公開情報だけで、知床遊覧船のような観光ブラック企業を見抜くことは、至難の技なのだ。
ただ、今回事故を起こした知床遊覧船の情報を精査していくと、ひとつの判断基準になるかもしれない観光ブラック企業の特徴が浮かび上がる。
それは、公式WebサイトやSNSの更新である。
先ほど申し上げたように、知床遊覧船のWebサイトをパッと見だけでは“ブラック感”はまったく伝わってこないが、注意深く精査していくと、ひっかかる点がいくつかある。
まず、「ブログ」をのぞいてみると、最新記事は19年8月となっている。2年9カ月もの間、情報が更新されていない。さらに、Webサイトに埋め込まれているFacebookを確認すると、投稿は20年8月で終わっている。こちらも1年9カ月更新されていないのだ。
もちろん、知床で小型観光船によるクルージングツアーは、1年の中で5〜9月下旬という短い期間しか運航できないので、他の観光業者に比べてそこまで頻繁に情報を更新することはない。だが、それを考慮しても知床遊覧船の放置ぶりは異彩を放っている。
例えば、同じ知床小型船協議会に加盟している同業者の中には今年1月にSNSを投稿しているところもある。また、大型船で知床クルージングができる「知床観光船おーろら」もGW前に告知するために、Facebookを4月20日に更新している。
関連記事
情報を更新しない
ご存じのように、観光業にとってWebサイトやSNSでの情報発信は非常に大きな意味を持っている。今の観光客はネットで情報を検索するからだ。
昔ながらにガイドブックやパンフレットを見て、宿泊先やアクティビティを申し込む人もいるかもしれないが、ホテルやツアー会社のWebサイトやSNSをチェックして、「ちゃんとしたところみたいだな」と安心して予約をする人が多いだろう。
そこに加えて、今回の観光船のように大自然を相手にするようなツアー業者ともなれば、SNSを使ってのこまめな情報発信は別の意味もある。同業者である「知床クルーザー観光船ドルフィン」の以下の投稿が分かりやすい。
『昨日から不安定な海上状況が続いております。明日までは欠航で確定しましたが、12日〜13日あたりまではイマイチな予報ですので、クルージング以外の予定も計画されておいた方が良さそうです』(Instagram 21年8月9日)
遠方からクルージングを楽しみにやってくる観光客のことを考えれば、最新の海の状況や運航情報などを事前に伝えておくことで、無用なクレームを避けることもできるし、釧路観光全体の満足度にもつながるのだ。
そんな“観光業の生命線”といっても過言ではないWebサイトやSNSを、知床遊覧船は2年近く放置している。ということは、2年ほど前からこの会社の内部で何かしらの大きな問題が発生して、従業員が定期的に情報発信をする余裕もないほど疲弊していた、と考えることもできるのだ。
まさしく、豊田船長が言っていたように、従業員たちが「ブラック企業で右往左往」していて、とても更新作業などできる状態ではなかった可能性があるのだ。実際、知床遊覧船の内部のゴタゴタを振り返っていくと、同社の“やる気のない情報発信”と見事にリンクしている。
報道によれば、同社がおかしくなったのは現在の桂田社長が経営権を買い取った17年ごろからだということだが、このFacebookがスタートしたのも17年3月。ただ、この5カ月間、なんの情報もアップせずに、更新するのはプロフィール写真だけというグダグダな感じだった。
同年8月になると、桂田社長が経営する「国民宿舎桂田」の情報や、系列のゲストハウスの紹介など6件の投稿があるが、同業者のようにクルージングの様子を紹介したり、欠航情報などを伝えることはない。
関連記事
「急速にブラック化」の可能性
そんな際立った「やる気のなさ」は翌18年に、さらに拍車がかかり、地震の影響を伝える2件のみとなって、19年はついにゼロになる。Webサイト上のブログ更新が途絶えるのも、この時期だ。
だが、そんな開店休業のFacebookが20年8月に突然、復活する。知床小型観光船協議会のクラウドファンディングプロジェクトで600万円近くが集まったという御礼が掲載されるのだ。このときのプレスリリースをみると、協議会の「会長」は桂田社長になっており、このような主旨が説明されている。
『本年は集客不振により未だに数便しか運航できないという壊滅的な状況であり、資金繰りや雇用の維持など日増しに危機意識が高まるばかりです。そこで、知床小型観光船の未来のため、この現状を打破するべく、クラウドファンディングに挑戦することを決意いたしました』(有限会社ホワイトリリー旭川 プレスリリース 20年7月21日)
ただ、奇妙なのはこのクラウドファンディングを境に再び、更新がプツリと途絶えてしまうことだ。クラウドファンディングはネットやSNSを使って呼びかけるものなので、その前後は情報発信が活発に行われがちだ。実際、同業者は20年7月以降、いろいろな写真をアップするなどしている。
しかし、知床遊覧船のFacebookは沈黙する。同社の中ではクラウドファンディングどころではなく、リストラの嵐が吹き荒れていたからだ。同社の元船長が地元メディアの取材にこう述べている。
「統括と営業部長は2020年の12月に首になった。自分を含めて季節雇用3人は契約を更新しないと通告された」(北海道ニュースUHB 4月26日)
そして21年に入ると、ベテラン船員など合わせて5人が一斉に会社を離れることになって、甲板員だった豊田さんが「格上げ」となり船長になったという流れである。
つまり、同業者が積極的にSNSを活用しているのに、知床遊覧船はほとんど更新することなく、20年ごろに休眠状態になってしまったのは、この会社が17年から急速にブラック化が進行して、「それどころじゃなかった」可能性があるのだ。
関連記事
「顧客目線」が欠如
誤解なきように言っておくが、「公式WebサイトやSNSを更新していない観光業者はすべてブラック企業だ」などと主張したいワケではない。民宿やホテルなどはシンプルに人手が不足しているので、WebサイトやSNSの更新にまで手が回らないこともあるだろう。SNSが開店休業状態でも、しっかりとしたサービスを提供している観光業者も少なくないはずだ。
ただ、先ほども述べたように観光業、特に大自然の中で人命に関わるようなアクティビティを提供するような会社の場合、SNSでの情報発信は、観光地の満足度向上だけではなく、そのツアーの安全を伝えるためには必要不可欠なものとなっている。
それが欠如しているということは、厳しいことを言わせていただくと、「顧客目線」が欠如していることでもあるのだ。今回のような杜撰(ずさん)な安全管理が招く事故というのは往々にして、利用者側の視点が欠如している会社が起こしている事実がある。
「WebサイトやSNSの更新」というのは、その会社がどれだけ「外の世界」に向き合っているのかを示している部分もある。観光業という外の世界の人々とのコミュニケーションが必要不可欠な業種で、それをやっていないのは、組織として何かしらの問題がある可能性もあるのだ。
もちろん、それ以前に観光客側が安心してツアーを利用できる環境整備が必要であることは言うまでもない。本来は、国や自治体が観光ブラック企業をしっかりと行政指導して、悪質な場合は営業停止処分などを下すのだ。
知床遊覧船はこの1年で事故を多発しており、行政指導で社名も公表されていれば、このような悲劇を避けれた可能性もある。しかし、事故は表沙汰にならなかった。
弁護士などの専門家によれば、これは小型船クルージングなどをやっている観光業者は中小零細が多いので、厳しい処分を下すと経営がすぐに傾いてしまうからだという。これは要するに、「小さい会社の悪事はお目こぼしされる」ということだ。
日本の会社は99.7%が中小企業ということもあって、「中小零細企業を倒産させなければ地域経済は発展する」という思想のもと、過度な中小企業保護政策が行われていた。
もちろん、成長している中小企業を応援することは大切だ。が、日本は「小さい会社」という条件を満たしているだけで、手厚い保護を受けられる。その結果、安全よりコストカットを重視するような観光ブラック企業まで守られてしまっているのだ。
関連記事
「退場」させるべきだった
厳しい言い方をさせてもらうが、知床遊覧船のような会社は潰れていたほうが社会のためだった。「ブラック企業で右往左往」と疲弊していた豊田船長などの従業員も解放されて、他の会社へ転職できた。もうけがなくなって困るのは、桂田社長ただ1人だけだったのである。
そして、何よりもこんな会社の船に、だまされるような形で乗せられて、冷たい海に放り出されてしまった24人の観光客の無念を思えば、知床遊覧船と桂田社長には、国の行政指導によって早く知床観光から「退場」してもらうべきだったのではないか。
本来は国が責任をもって厳しく取り締まるべき観光ブラック企業を、「経営基盤が弱いから」という理由で「延命」させたことで、結果として多くの尊い命を奪うことになってしまった。
「中小零細企業を倒産させない」という過度な保護政策よって、結果的に低賃金重労働を常態化させて、多くの人々を経済死させている現在の日本の状況と妙に重なる。今回の事故も、国土交通省をはじめとした政府の罪が重いと感じるのは、筆者だけだろうか。
最後になりましたが、亡くなられた方たちのご冥福を心からお祈りします。合掌。
関連記事
Bagikan Berita Ini





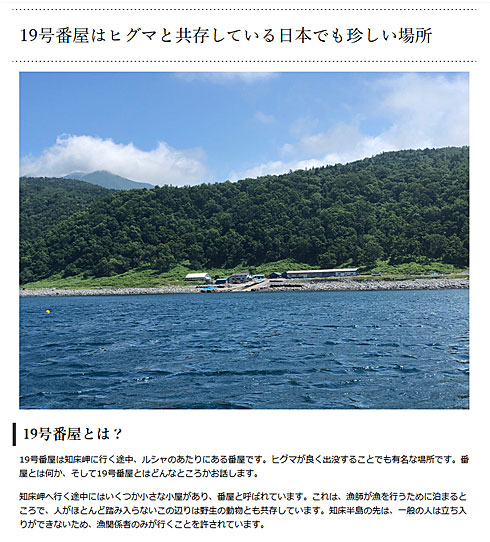




















0 Response to "知床遊覧船のような「観光ブラック企業」は、どのような特徴があるのか - ITmedia ビジネスオンライン"
Post a Comment